 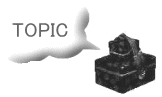 |
2005年 8月号 月刊テアトロ 劇評
宇宙全体に溢れる愛
京楽座「しのだづま考」
―演劇評論家・結城雅秀―
|
京楽座の「しのだづま考」。
脚本と演出がふじたあさや。中西和久のひとり芝居である。
日本の伝統的文化に取材するものであって、物凄いパワーだ。
それに、技術が的確で、モノローグ演劇の新しい境地を開拓したと言い得る。
冒頭、信太山盆踊で始まるのだが、その際の細やかな指使いに引き込まれた。
中西は、直ちに解説者となり、中世の説経節の説明を始める。
パネルになった和泉市の地図を取り出し、「しのだづま」の伝説を紹介する。
そして、それを実際に演じて見せるのだ。
説経節であり、講談であり、浄瑠璃である。
女形はもちろん、子役、善人、悪人をたくみに演じ分けて、観客を興奮させる。
前半は、篠田の森の子狐が葛の葉に化身し、安倍保名の妻となるが、真の姿を自分の子どもに見られてしまい、「恋しくば・・・」の歌を残して、去っていく物語。
これには続編があり、その子供が成長の上、安倍清明となって、超能力をもって宮中における地位を確保していく。
実に痛快であり、パロディーも利いていて楽しい作品になっている。
物語に深い共感を覚えた。
説経節は講談や浄瑠璃の形に発展していくのだが、元来は僧侶が民衆に仏教の教えを説いたものであるとか。
物語の前半、葛の葉が身を隠す際に、七年間に及ぶ家族との生活という執着に悩まされるが、「この世はかりそめのもの。執着してはならない。」との哲学を説く。
こういうところに説経節の原型が残っているのであろう。
人間は、愛し、生きる現象的存在である。
そして、この宇宙は愛に溢れている。
こうしたことを考えさせてくれた中西和久はまさに天才である。
(2005年5月29日 新宿・紀伊國屋ホール) |
 |
|