 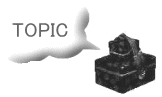 |
「週刊金曜日」 より きんようぶんか
中西和久『しのだづま考』
父の抑留地でひとり芝居
―中村ひろみ (ライター)―
|
九月中旬、俳優中西和久は自身の代表作であるひとり芝居『しのだづま考』をロシア各地で公演した。
エカテリンブルグ国際演劇祭への参加を皮切りに、シベリア鉄道に揺られながら大平原の町々をめぐる19日間の旅。それは、戦争を体験した父親との不思議な「縁」を感じる旅でもあった。モスクワ芸術座で千秋楽を迎え、九月末に帰国の途についた中西に話を聞いた。
中世の放浪芸・説経節を題材とした『しのだづま考』は人間と女狐との悲恋物語。民話の「狐女房」が元となっていて、叙情性をたたえた舞台は高い評価を得ている。
「59歳で亡くなった親父は、敗戦後の数年間ロシア(旧ソ連)の収容所に抑留されていました。
生前はそのことに一切触れてはいけない気がして、互いに話すことも聞くことも無かった」という中西。
今回の公演は不思議な縁を感じるものだった。
「父の遺品を整理していたら、抑留時代の手紙や手記が出てきました。ウラジオストクから日本に帰る直前、家族に宛てた捕虜用葉書というのがあって、『生きて帰れる』という喜びが細かい字でびっしりと書かれていて、胸がつまりました。」
父の足跡追い求めて
2002年日本に返還された抑留者リストの中に、福岡県出身の「中西重雄」という名前があった。
中西の父・重雄は日大芸術学部出身だった。
シベリア抑留時代、捕虜の身の辛さを慰めたいと重雄が呼びかけて収容所内に福岡県出身者を中心にした劇団が結成された。
劇団の名前は「博多座」。
「芝居をやると収容所内で黒パンの配給がよくなった、という書付も残っていて、思わぬところで演劇の経験が役に立ったようです」。
ロシア各地の収容所18カ所を転々とした父・重雄。
見知らぬシベリアの地で、「博多座」の公演が続いた。
「どげな芝居をしとったかね〜」―感極まると九州訛りが抜けない中西は、父の思いを測りかねながらも、
「親父は現代演劇にかぶれとったけど、もともとは旅芝居一座の生まれ。ロシアの地でも日本恋しやの浪花節的な芝居をやっとったんじゃなかろうか」。
遠く離れた故郷を思いつつ、収容所の仲間たちと心を寄せ合っていたのではないか。
「生きている間はそんなこと一言も話をせんかったなあ」。
あるとき、福岡公演で帰郷した中西の楽屋へ、一人の高齢の男性が訪ねてきた。
「私はあなたのお父さんのお芝居をロシアの収容所で見たことがあるんですよ」。
突然のことで戸惑いながら、「親父の過去に触れたような気がしてうれしかった」と中西は言う。
父はどんな思いでシベリアの抑留時代を生き延びてきたのか。
今回、中西はエカテリンブルグ国際演劇祭への招待公演を初めとして、元収容所近くのオムスク、トムスク、そしてモスクワと各地で公演を行なった。
エカテリンブルグからオムスクまではシベリア鉄道に揺られて約15時間、トムスクまではさらに鉄道で17時間。
トムスクからモスクワまでは、ノボシビルスク経由でバスと飛行機を乗り継ぐ過酷な行程だった。
それはロシアでの父の足跡を追い求める旅でもあった。
「9月というのにまるで真冬のような寒さ。九州育ちの親父には、シベリアの厳冬はさぞやこたえたろうと思います。」
父親が抑留されていた収容所にほど近いと聞かされていたオムスク、トムスクは、想像以上の大都市で、ロシアの工業化のシンボルともいえる町だった。
劇場がいくつもあり、人々は日常的に演劇や音楽を楽しんでいる様子がうかがえた。
「学生からお年寄りの夫婦まで気軽に芝居を楽しんでいる。うらやましい雰囲気だった」
最後は総立ちで喝采
9月12日から6日間にわたって開催されたエカテリンブルグ演劇祭では、『しのだづま考』における伝統の継承と創造の成果に対して「テアトラーリヌイ・セゾン賞」が贈られた。
国際演劇祭の場合、同時並行で数ヶ所の舞台が上演される。
「観客は最初の10分で面白くないと、席を立って他の劇場に移ってしまう。ぼくの芝居は時間が経つごとにどんどん観客が増えていって、最後は総立ちの拍手喝采!」
日本語という言葉の意味は伝わらなくても、語りのリズム、うねり、感情の流れはしっかりと観客の心に届いたと実感した。
「演劇のことばは、まさに心を伝えることば。演劇的な言語がストレートに伝わっていく感動を味わえた」
最後の公演地モスクワでは思いがけず、モスクワ芸術座の舞台に立つことができた。
「まさか!って感じだった。直前まで公演会場が知らされてなくて、まさか自分がモスクワ芸術座の舞台でやれるなんて思ってもいなかったからね」
夢にまでみた現代演劇の殿堂は、意外なほど質素だった。
「劇場の椅子は小ぶりで堅い木製。貧しい学生やインテリたちが集まり、『時代の最先端を表現してきた劇場』という雰囲気が今も残っている」
何気なく腰を下ろした観客席が、「そこは演出家のスタニスラフスキーの定席だったんだよ、と言われてビックリ仰天(笑)。スゴイとこに来たんだなと、ゾクッとした」。
劇場内の中ホールで行われた『しのだづま考』公演は、モスクワ芸術座で演劇を学ぶ学生や教授などを中心に、熱心な観客を集めた。
「東洋の現代演劇がこれほどまで若い観客層に熱狂的に受け入れられtことはこれまでになかった。今後の日露の文化交流に大きく貢献した」と、モスクワ芸術座付属演劇大学学長からも高い評価を受けた。
「東洋からやってきたリアリズム演劇のニューウェーブ」として注目を集めた中西のひとり芝居。
「ロシアでは今、リアリズムや伝統的な演劇をどう改革していくか、打開していくかが大きなテーマになっている。そうした手法のひとつとして、中世の説経節を素材としたぼくの芝居が興味をひいたようだ」と中西はいう。
ソ連からロシアへと体制が変わり、人々は新たな伝統を求めていると中西は強く感じた。
ロシア国内はどこも貧富の差が大きく、日本以上の格差社会が生まれている。
民族差別も激しさを増し、一方でヨーロッパ諸国への抜きがたいコンプレックスと経済成長による自意識とが複雑にからみあっている。
「芝居を観たり、音楽を聴いているときはみんな一緒でも、それが終われば、あからさまな差別や貧富の差が目の前に現れる。ロシアは厳しい状況だ」。
モスクワ芸術座には父・重雄も60年近く前に訪れている。
演劇専攻の学生だと言う重雄に、ロシア人将校は疑いの目を向け、モスクワ芸術座の舞台の構造を説明してみろと連行した。
「親父が捕虜として連れて行かれた劇場の舞台に、自分が役者として立っている。不思議な気持ちでした」。
生前、ロシアでの抑留時代のことは一切口にしなかったという父・重雄。
一度だけ、幼い和久がこいのぼりの幟に書かれた自分の名前を見て
「なんで和久と付けたと?」と尋ねたことがあった。
父はこう答えたという。
「平和が久しく続くようにタイ。」
(敬称略)
(2008年10月31日 週刊金曜日 725号) |
 |
|