 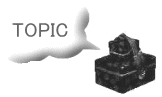 |
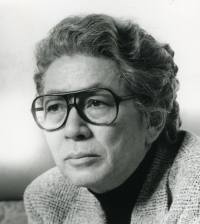 京楽座 『破戒』 への期待 ①~⑥ 京楽座 『破戒』 への期待 ①~⑥
五木寛之
2006年10月11日~18日
日刊ゲンダイ
「流されゆく日々」
連載7591~7596回に掲載 |
| 【連載①】 |
中西和久といえば、知る人ぞ知る平成演劇界の風雲児だ。紅テント、黒テント、また寺山修司や福田善之らの昭和演劇の疾風怒濤時代と重なっていれば、民衆演劇の担い手として、さぞかし若い観客を熱狂させたことだろう。
かつての説経芝居の伝統をつぐ中西の舞台は、最後衛が最前衛でもあるという、ひとつのあかしであった。京楽座をひきいての長年の活動は、昭和の激動期のリアクションとしての非リアリズム的演劇界を逆照射する輝きを放ち続けてきた。
その中西和久が、島崎藤村の『破戒』を上演するというニュースを伝えてくれたのは朝倉俊博である。
いまどき藤村?いまどき『破戒』を?という印象を抱く人は少なくあるまい。じつは私もその一人だった。泉鏡花ならともかく、島崎藤村ですか、と言う編集者もいた。その反応はもっともである。藤村という作家のイメージが、どこか教科書的なのだ。同じ古典的作家でも、漱石、鴎外とくらべてなんとなく地味なのだ。
しかし、そういう月並みなイメージは常に誤っている、という私の持論にしたがえば、藤村という作家はなかなかおもしろそうではある。若い頃は恋愛詩を書き、のちには大スキャンダルもまきおこした人物だから、カビ臭い風貌の背景に、なまなましいエランビタールを秘めた小説家なのではあるまいか。
そもそも『破戒』や『夜明け前』などの長編は、ちゃんと読まれているのだろうか。
「木曽路はすべて山の中である」とか、「蓮華寺では下宿を兼ねた」とか、冒頭の文章こそよく知られているわりに、中身が話題になることはほとんどないといっていい。
ここはひとつ勉強までにと、原作を読み返し、中川小鐡脚本の監修を買ってでることにした。
小説『破戒』は、いま読んでみても相当に面白い。M・ゴーリキーの『母』や、初期のプロレタリア小説とちがって、差別問題を単なる思想小説にしていないところがいい。人間の描写が、みずみずしいのである。脚本ではそれがさらにふくらみを加え、時間超えて人びとをひきつける青春の劇になっていることに感心した。いい舞台になりそうな予感がある。
|
| 【連載②】 |
芝居というものは、人間の情をゆり動かすものだと、私はずっと思ってきた。情を動かすのではない、知を震撼させるものこそ演劇である、という思想が主流であった時代も、ずっと一貫してそう言い続けてきた。
小市民たちの眠れる意識、船底にこびりつく水垢のような古い常識に一撃をくわえ、新しい風の中にさらそう、というのが戦後の演劇の思想だったと言っていいだろう。異化作用という言葉が、スターシステムという言葉にとって代わる時代である。
私はいつも、新しいものより古いものが新しいと考えてきた。ブレヒトが大流行していた時代にも、ブレヒトはひどく常識的、教条的な理論のように感じてきた。
小説の世界における物語性の克服、詩の世界における抒情の否定、などと同じように、演劇ではメロドラマは常に目の敵にされ、嘲笑の対象となってきたのである。
音楽や詩の世界でも、メロディーは古く、リズムこそ新しい、といった見方が横行していた。しかし、それらはいずれも、私に言わせれば近代主義の古い燃えかすに過ぎない。
ブレヒトの方法論が常識になったとき、ブレヒトは死ぬ。だれ一人ブレヒトを認めようとしない時にこそ、ブレヒトは新しいのだ。
「人を泣かせるのは簡単だ。でも、自分は人を笑わせる役者になりたい」
とは、かつての大アイドル・スターの宣言である。
その言葉をきいたとき、たしかに私は笑った。本当に人を泣かせることが、それほど簡単にできるのか?
目頭がちょっとうるむくらいの芝居なら、べつに難しくはないだろう。だが、観客を本気で号泣させることが、どれほど困難なことか。
「お涙ちょうだいのメロドラマ」などという。しかし、「お涙頂戴」とはなんというキッパリした覚悟だろう。「お命頂戴つかまつる!」と捨て身の太刀をふるうのと同じ覚悟がそこには必要なのだから。
差別という主題を、啓蒙的に観客に説き聞かせる芝居は、いつの世も多い。しかし情の側から知を攻めるのが演劇だと私は思う。『破戒』は、芝居の素材としてまちがいなくおもしろい。中川小鐡さんの脚本を読んで、そう思った。はたしてどんな舞台になっているだろう。なんとかして劇場にかけつけねば。
|
| 【連載③】 |
これからはドフトエフスキーよりトルストイのほうがおもしろい、と、どこかに書いたら、さまざまな反響があった。
一笑に付されても不思議のない発言だが、なにかビビッとくるものがあったのかもしれない。
トルストイも、ドフトエフスキーも、ともに宗教的作家である。宗教的という冠をつけることで、なにか大文豪の価値がさがるように感じる読者もいそうだ。しかし両者とも、神という光源のもとに人間をおき、その存在を確認しようとした小説家であることにかわりはない。
しかし、宮沢賢治を例にあげるまでもなく、文学から宗教色を脱色することで文学者の域にとどめようという志向は、現在でも一貫して日本の文芸ジャーナリズムの中に流れている。
トルストイの『復活』は、島村抱月×松井須磨子の舞台によって日本でも最もポピュラーになったトルストイの小説である。
♪ カチューシャかわいや わかれのつらさ ♪
と、いう、我が国のレコードによる大ヒット歌謡の第一号といわれる劇中歌は、抱月と相馬御風(そうまぎょふう)の作詞によって津々浦々にうたわれた。
相馬御風は、良寛の研究者としても知られる文学者で、例の「都の西北 早稲田の森に」の早大の校歌を作詩した人だ。
この『復活』は、史上まれといっていいほどの大成功を収めた。そしてカチューシャと青年貴族ネフリュードフとの愛の物語として天下の子女の紅涙をしぼることになる。
この『復活』というタイトルに、高校生だった頃の私は、「恋の復活」「愛の復活」というイメージを抱いていた。「ふたたびの愛」という物語を想像していたのである。『復活』という邦訳題からすると、そう考えたとしてもなんの不思議もあるまい。
後にロシア文学を噛る様になって、原題が「ヴァスクレセーニェ」であることを知った。直訳すれば、「日曜日」であり、また「復活祭」のことである。『復活』と『復活祭』とでは、大変なちがいである。『復活祭』は、キリストのよみがえりを記念する大事な宗教的行事だからだ。
|
| 【連載④】 |
『復活祭』といえば、かつてサンクトペテルブルクのドストエフスキー記念館を訪れたときのことを思いだす。
春先で、道路端にはまだ汚れた雪が残っていた。『罪と罰』の舞台となった一画を歩き、ラスコーリニコフがさまよった露地を抜けて、灰色のドストエフスキー記念館へいったのだ。
文豪が作品を書いた書斎の机の前で感慨にふけっていると、体格のいい女性が現れて、ドストエフスキーに関心があるのか、とたずねてきた。
「大いに興味がある」
と答えると、
「どういう作品を読んだか」
と、たずねる。「カラマーゾフの兄弟」をあげたら、わが意をえたりというようにうなずいて、書斎の前に張ってあるロープをはずし、中へ入ってよく見なさい、と言う。そしてわたしをドフトエフスキーの机のそばに引っぱっていき、椅子に腰かけろ、とジェスチュアで伝えた。そんなことをしてもいいのだろうか、と私がちゅうちょしていると、
「館長のわたしが許可します。」
と言った。どうやら本物の館長らしい。こんな機会はめったにあるまい。私はドフトエフスキーが原稿を書いたであろう机の前に坐って、深刻そうな表情をつくってみたが、気のきいた文章は一語もうかんでこなかった。
わたしはそのあと、たくましい女館長と、しばらく話をした。片言のロシア語でも、業界の話題はけっこう通じるものである。私が東京でドフトエフスキー没後百年の記念の会を講演した、と言うと、彼女はびっくりして私を点検するように眺めた。とてもプロの作家には見えなかったのだろう。
別れるときに、女館長は私の手の上に二個の極彩色の模様を描いた卵をのせて、
「復活祭の卵よ。毎年、自分で作るの」
といい、何か祈りの言葉のような文句をつぶやいた。彼女が口にした「ヴァスクレセーニェ」という単語の響きだけが、妙に頭に残った。
話が脇道にそれたが、『破戒』という題名は、何を意味するのだろう。破戒とは、戒を破ることである。この言葉には、一般的に二つの用いられかたがあるようだ。一つは世間でいうところの「訓戒」(いましめ)である。もう一つは仏教でいう「戒・律」である。具足戒、五戒などというやつだ。藤村はどういう戒のイメージをもって、この題をつけたのだろうか。
|
| 【連載⑤】 |
先週末、ようやく『破戒』の舞台を観ることできた。
熱気を極力抑えて、静かな決意を感じさせる良い舞台だったと思う。こういう志を秘めた芝居は、えてして演じる側が気負いがちなものだ。自分たちは意義のある舞台を演じているのだという思い入れが、どうしても生でほとばしってしまう。一段高いところから観客に説教をたれているような芝居が少なくないのである。私は昭和二十七年ごろ、池袋の西口にあった舞台芸術学院に、もぐり学生として遊びにいったことがある。講習科、いわゆる夜間部に親友がいて、誘われたのがきっかけだった。
彼の卒業公演のときは、舞台の美術の手伝いをした。『第三帝国の恐怖と貧困』とかいう芝居だったと思う。当時は意識の低いプチプル的な観客を、演劇を通じて目覚めさせるという気構えだった。人民に服務する、などと口では言いながら、気分はプロレタリアートの最前衛のつもりで気負いまくっていたものだ。
そんな往時を思いだしながら、芝居も成熟したものだな、と、思った。むしろ熱気は客席のほうに充満していた。一席の空いた椅子もない超満員である。よく批評家や記者のための招待席が、歯が抜けたように空いている恥ずかしい光景が見られるが、こんどの『破戒』の客席は、かつての紅テント、黒テント時代を思わせる混みかただった。
芝居の中身のほうも、なかなかである。なんといっても、姿を見せない語り手の三国連太郎さんのナレーションが実にいい。年季の入ったプロの仕事というのは、凄いものだ。絶品といっていい語りだった。
ライブで演奏される音楽も魅力があった。脚本では『ふるさと』となっていたので、いささか気になっていたのだが、アレンジで教科書ふうの原曲が、がらりと生き返っている。
土取利之さんの舞台音楽がいい例だが、大編成のオーケストラなど使わなくっても、十分に効果があがるものなのだ。
主役の瀬川丑松(うしまつ)を演じた中西和久さんは、後半になればなるほど生彩をはなってくる。主役以外の共演者たちが、なかなか存在感のある達者な役者ぞろいなので、最初は丑松がややひよわに感じられるのだが、勿論それは中西さんのしたたかな計算にちがいない。
ヒロインの志保を演じる女優さんがとてもいい。『イルクーツクの物語』をやっていたころの奈良岡朋子さんを、ふと、思い出してしまった。
|
| 【連載⑥】 |
演出の西川信廣さんは、こう言っている。「感動を共にした人間同志はけっして差別したり殺しあったりしない」「人間には想像力がある。それを信じる」。この二つの言葉からの視線と視点でこの作品を演出した、と。
この言葉には全面的に共感する。
差別とはどういうものか。そして、それをどう乗り越えていけばよいか。それを知識として学ぶことは大切なことだ。知らない、ということは、それ自体が犯罪であることさえある。
今でもしばしば言われることだが、東京出身の人には差別について何か誤解している向きが多いようだ。
「イツキさんは福岡の出身だから、差別とかそういうことに実感があるでしょうけど、私たち東京にはあまりそういうケースがないもので、頭では理解していてもなかなか実感がわかないんですよ。」
そう言われて、首をかしげることがしばしばある。差別が制度化されたのは、江戸ではなかったのか。東京は差別の王城であったと私は思っている。
たしかに知らないことは、それ自体、悪であると言っていい。しかし、演劇の教育的意義を否定はしないけれども、舞台から教えられるようなのはご免だ。西川さんが言うように、共感ということこそ、芝居の武器だろう。感情移入を否定するのが二十世紀の新しい演劇の底流だった。予定調和を嘲笑したのも、そのひとつだ。情緒的であること、感傷的であること、センチメンタルであること、などを、私たちはどれほど恐れ、軽蔑してきたことか。
人を泣かせる芝居などというものは、触るのはもちろん、目にするだけでも汚れるという感じだった。インドで不可触民を見ることすら恐れるのと似ていた。
知的な演劇、そして知的な観客、さらに知的な批評のつくりだす乾いた空間こそ、本当の共感を拒否してきたのだ。そして、笑いは高級で、涙は低い、という見方は、いまでも根強い。『破戒』は、いい芝居だった。共感するものも多かった。しかし、それだけにいま一つ、突き抜けてほしいという期待もないではない。
あらゆるジャーナリズムの批評や、専門家の評価を意識せず、嘲笑と無視の中に孤立する演劇。そういう舞台を見てみたいものだ。
|
 |