 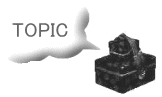 |
中西和久の『ピアノのはなし』の面白さについて
演劇評論家 七字 英輔
|

わが国には「語り物」という口承文芸の一ジャンルがある。古くは平家琵琶や説経節、比較的新しくは講釈(談)や浪花節などがそれに当たる。滑稽な「落し咄」を祖とする落語もその変型のひとつといっていいだろう。近年のひとり芝居の流行は、そうした伝統につらなるものと私は考えているが(ひとり芝居は何も日本の専売特許ではないが、西洋のひとり芝居は、ベケット作『クラップの最後のテープ』のように、たとえテープから聞こえてくるのが自分の声であっても、基本的には対話を旨とした「劇」だといっていい)、それは中西和久の説経節ひとり芝居『しのだづま考』『山椒大夫考』『をぐり考』の三部作が、説経節のみならず、越後瞽女歌、歌舞伎狂言、講談、近代小説などを自在に織りなしながら観客に直接語りかけてくることによって典型的に示している。
同じように公演回数を重ねている『ピアノのはなし』についても、中西の卓抜な「語り」が舞台を進行させていく。しかしそれにしても、この『ピアノのはなし』は前三者に比べていかにも異色である。下手に演奏者のいるグランドピアノと奥に小学校で使う跳び箱とボール玉三個が転がっているだけの簡素な舞台。演奏者によるピアノ曲が流れる中、中西が登場し、日本に初めてピアノが現れたときからのピアノ受容の歴史を語り、いったん退場する。ここまでが劇の前半。やがて燕尾服の正装で再び舞台に現れた彼は、頭を白く染め、杖をつき足を引きずっている。中西はここでは、ドイツで生まれ、日本に渡ってきて、半生を佐賀県鳥栖の小学校で過ごしたというピアノ自身に変身しているのだ。そして語りだすのが『月光の夏』として映画、小説などを通して今や多くの人に知られるようになった、敗戦間近のある日、明日は出撃という特攻隊員が二人、鳥栖小学校を訪ねてきて、ベートーヴェンの「月光」を弾いて基地に帰っていった挿話をはじめとする戦中、戦後の回想である。『ピアノのはなし』はまさしくピアノの語る話だった。
 私はこの構成の妙に舌を巻いた。前半と後半を日本唱歌のピアノ演奏でつなぎ、最後には再び、ピアノソナタ第14番「月光」が会場を包む。いや、途中にも折に触れ、ピアノは音をたて、曲を流す。前半と後半で物語る主体が変わること、演奏がその語りに付かず離れず伴走しながら情景を描き出していくことなど、私はこの劇をまるで一曲の能のように感じたものだ。ピアノが奏でているものは、能でいえば地謡のそれにも等しい。中西の「伝統」への通暁は、こういうひとり芝居の転用にも表れている。 私はこの構成の妙に舌を巻いた。前半と後半を日本唱歌のピアノ演奏でつなぎ、最後には再び、ピアノソナタ第14番「月光」が会場を包む。いや、途中にも折に触れ、ピアノは音をたて、曲を流す。前半と後半で物語る主体が変わること、演奏がその語りに付かず離れず伴走しながら情景を描き出していくことなど、私はこの劇をまるで一曲の能のように感じたものだ。ピアノが奏でているものは、能でいえば地謡のそれにも等しい。中西の「伝統」への通暁は、こういうひとり芝居の転用にも表れている。
舞台は、特攻隊員たちの生前のスクリーンに映写されるなか、中西が特攻隊員たちの遺書をひとつひとつ読み上げ、やがて日本国憲法第九条の条文が映し出されて閉じられるが、古典芸能としての能が、現世に思いを残して死んだ死者への追悼、遺籍に発していることを考えれば、いかにもこの劇のラストに相応しい。『ピアノのはなし』の感動は、内容はもとより、その形式からもたらされたと思うのは私だけではあるまい。

|
|
|